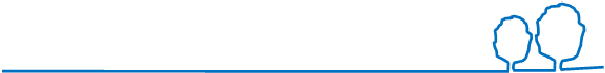
●
その他の活動
講演会/学習会
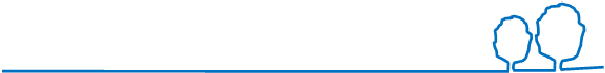
●
その他の活動
講演会/学習会
|
| |
講演会『ことばはふつうにゆったりと』―小児科医の現場から (2014年10月19日) |
|
梅村浄さんのお話は、なにか、ほっとさせられるものがありました。 小児科医というお仕事柄、ことばが遅いという悩みを持つ母親の相談にのることが多いそうですが、基本はゆったりと自信を持って接するということ。 この数年何回も行っているというモンゴルの障がいを持った子どもたちとの交流のお話も興味深いものでした。自然のなかに人間の暮らしが包まれている豊かさが、今の日本に欠けているのではないか。そのことを意識していくことが大事だといったお話でした。 (スタッフ加藤) |

|
『ちづる』上映会&赤﨑監督講演会
(2013年9月29日)
|
|
『ちづる』の上映会と監督の講演会を、50名以上の観客を集めて行なうことができた。場面は三つあった。映画会、監督のトーク、茶話会である。茶話会には「きょうだい」の方も何人も参加していた。それぞれのスタンスがあって、そのことを率直に話してくださった。この一時間あまりの時間が参加者それぞれにとっての何かの「きっかけ」になれば幸いだ。私にとっては何の「きっかけ」になったのか。自問しています。
(スタッフ加藤)
|
|
講演会『自立生活を考える(講師 野上さん・山崎さん・岩橋さん)』
(2012年3月4日)
|

先日、学びの広場にて、自立生活を送っている野上さんと山崎さんと支援を担っている“たこの木クラブ”の岩崎さんにお話を伺いました。副題にもなっている『それぞれの自立生活への道と自立生活獲得のための支援』ということで、質問形式で具体的に1人暮らしやグループホームで生活することになった経緯やその折々の様子、そのつどの気持ちなどを語っていただきました。また、支援する側からの現状や思いなども話していただきました。おふたりは、いろいろな事業所を使い、いろいろなヘルパーさんとともに生活されています。大変さももちろんあるのでしょうが、自分で選んで納得 して生活されているように感じました。ひとそれぞれ自立の仕方は違います。「こう生活したい」という思いをキャッチして、 タイミングを大切に、生活の仕方を選んでいけばいいのでしょうか。 講演会の後、様々な声が聞かれました。「生活のスタイルがわかって身近に感じられた」
「やろうと思えば、いつでもすぐにできることがわかった」 「ヘルパーさんとずっと一緒はきついかもしれない」「精神的な自立が自立なのではないだろうか」「一番大切なのは、人とのつながりをつくること」などなど…。これからも、引き続きいろいろな機会にみなさんと、話し合い、考え合いたいと思います。
(スタッフ浜崎)
|
|
20周年記念講演会
「うちの子って普通じゃない?―小児科の現場から―」梅村こども診療所所長 梅村浄さん
(2007年3月4日)
|

|
広場に電車に乗って通えるだろう
か、不安でした。今は社会に出て
乗ったこともなかった線で会社に
通っています。先生のお話を伺っ
てまだまだ伸びる可能性があるの
だなと実感しました。
|
|
悩んでいたことにピンポイントで
答えてくれるようなお話でした。


|
「人生はチャレンジだからやった
らいい」(中略)前向きの言葉に
ふれ、背中を押された思いです。
浄らかな思いになれた学習会の第
二弾を期待します。
|
|
「普通」とは何か私もより考える問題です。しかし「普通」とは自分の価値基準であり、他人が決めるものではありません。あまりにも細分化した今の学校教育、医学的に病名をつけることで問題に取り組もうとしない学校に憤りを感じます。
|
|
学習会報告
|
|
2005年 第3回 学習会『目から鱗のデンマ-ク福祉最新事情』
━ 研修報告「子どもと家庭、障がいがある人への支援について」━ 日時:4月10日(日) 講師:静岡英和学院大学地域福祉学科助教授 NPO法人「学びの広場」代表理事大島道子 |

|
|
2004年 第2回 連続学習会 ②
日時:2月8日(日) 講師:自立生活センター・立川 副理事長 野口俊彦さん 内容:支援費制度のデイサービス、日中の通う場について等、地域でどのように生活して いくかについて。 2004年 第2回 連続学習会 ① 日時:1月18日(日) 講師:自立生活センター・立川 副理事長 野口俊彦さん 内容:自立生活センター・立川の活動内容、様子などをビデオを交えて。 |

|
|
2003年 第1回 連続学習会 ②
日時:5月11日(日) 講師:渡邊雅俊さん |

|
|
|
内容:
|
①職業生活への参加について
②安定した職業生活の継続について |
|
|
2003年 第1回 連続学習会 ①
日時:4月13日(日) 講師:渡邊雅俊さん |
||
|
静岡英和学院大学勤務(東京障害者職業センターにて生活支援パートナー
(ジョブコーチ)として勤務した後、知的障害者授産施設において、一般企
業就労支援のための職業リハビリテーション、就労相談を担当)
|
||
|
内容:
|
①働くことにハンディを持つ人たちの実態
②働くことを支えるしくみ ③働くことを支えるために |
|

|
||
|
|